雪虫の生態
代表的な「トドノネオオワタムシ」の場合
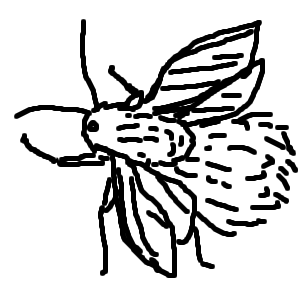
北国に冬の到来を告げる「雪虫の乱舞」。
尻に綿毛を持つこの虫は、まるで雪が舞っているかのように飛ぶ。
小中学生の頃、自転車で快走中に、その塊の中に突入してしまい、
体中「雪虫まみれ」になったことを記憶している。(口にも入った!)
ところで、この雪虫。実に奇怪な生き物なのであります。
![]()
第一世代
春①ヤチダモの木に産みつけられた1つの卵から、1匹のアブラムシが生まれる。
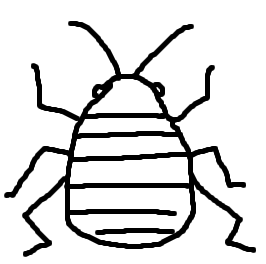
ところが、この時生まれるアブラムシは、
全てメス♀。このアブラムシは、ヤチダモの樹液を吸って成長し、木の葉の裏に
子虫を産む。第二世代
夏②ここで産まれる子虫も、全てメス♀。
同様に、樹液を吸って成長し、脱皮してサナギになる。
しかし、
動くことも樹液吸うこともできるサナギである。サナギから脱皮すると、羽のはえた成虫(?!)になる。
若い
トドマツを探して飛び、根の近くに子虫を産む。第三世代
秋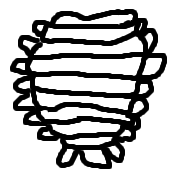
③ここで産まれる子虫もまた、全てメス♀。
今度は、その近くに住む
アリが、子虫をくわえて巣の中に連れていく。アリは、トドマツの樹液を吸ったアブラムシが出す「甘い排泄物」をもらう。
つまり、「
アリが、アブラムシを飼っている」といえます。ここで成長したアブラムシは、巣の中で
子虫を産む。第四世代
晩秋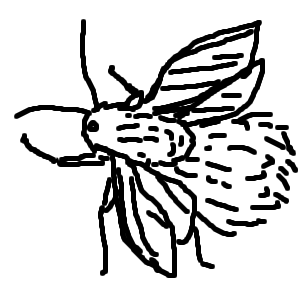
④ここで産まれる子虫もまたまた、全てメス♀。
この子虫が、アリの巣の中で成虫となるのが、晩秋~初冬。
この第四世代こそが、薄青紫がかった綿毛を持つ、いわゆる「雪虫」。
地上に出た虫たちは、群れをなして飛びます。これが、
「雪虫の乱舞」。雪虫の群れは、
ヤチダモの木を見つけると、葉の裏に子虫を産む。第五世代
初冬⑤ここで初めて、オス♂とメス♀の子虫が産まれる。
交尾後、ヤチダモの木の皮の間に、「
たった一個の卵」を産む。卵は冬を越え、春になると、また第一世代のアブラムシとなる。
![]()
今から20年ほど前、札幌市内でも結構な「雪虫の乱舞」を見ることができました。
しかし、ここ数年は、まったくお目にかかっていません。
かと言って一般のアブラムシ自体は、我が家の家庭菜園を食い荒らす「害虫」として、鳥肌が立つほど生息しています。
実は、雪虫になる種類のアブラムシも、結局は「害虫」。樹液を吸って、トドマツやヤチダモの木を枯らしてしまうのだそうです。
そこで、人間サマは、どうしたか?。
トドマツとヤチダモの木を、「雪虫」が飛んで行けないくらい遠くに離して植林するようにしているそうです。
雪虫の生態も奇怪で驚きでしたが、世の中には、そんなことを計画的にやっている人(道庁の人かなぁ?。営林署の人かなぁ?。林野庁の人かなぁ?。)がいるということにも驚いてしまいました。すごいですね。
でも、「初冬の風物」としての「雪虫の乱舞」が見られないのは、ちょっと寂しい気もします。(AKKI)
(参考文献:科教協北海道ブロック編著『北海道自然の話』新生出版)
![]()